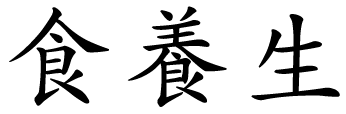サケがいない
 北海道の北東に位置するオホーツク海は、サケやマスをはじめとする漁業資源に恵まれた海域だ。北太平洋の環境を支えるこの海は、現在急速な温暖化により海氷の面積が大幅に減少しており、生態系や経済に深刻な影響が現れはじめている──。日本の北の沖合ではサケの漁獲量が激減しており、過去15年間で約70%下落した。北極からはるか南にあるこの地域の海岸には、一面の海氷が押し寄せてくるが、サケの消滅はこの海氷の消滅と同時に起こ衝撃的なこの出来事──サケと海氷の消滅──は、シベリアと日本に挟まれたオホーツク海の海水温が急速に上昇した結果だ。産業化以前の時代と比べると、この地域の気温は場所によっては3度も上がっている。世界で最も急速な温度上昇のみられる地域の一つだ。そのスピードは世界平均をはるかに超えている。2015年にパリで決められた、世界の平均気温上昇を2度以下に保つようにする、という限度も上回っている。
北海道の北東に位置するオホーツク海は、サケやマスをはじめとする漁業資源に恵まれた海域だ。北太平洋の環境を支えるこの海は、現在急速な温暖化により海氷の面積が大幅に減少しており、生態系や経済に深刻な影響が現れはじめている──。日本の北の沖合ではサケの漁獲量が激減しており、過去15年間で約70%下落した。北極からはるか南にあるこの地域の海岸には、一面の海氷が押し寄せてくるが、サケの消滅はこの海氷の消滅と同時に起こ衝撃的なこの出来事──サケと海氷の消滅──は、シベリアと日本に挟まれたオホーツク海の海水温が急速に上昇した結果だ。産業化以前の時代と比べると、この地域の気温は場所によっては3度も上がっている。世界で最も急速な温度上昇のみられる地域の一つだ。そのスピードは世界平均をはるかに超えている。2015年にパリで決められた、世界の平均気温上昇を2度以下に保つようにする、という限度も上回っている。「オホーツクの氷」の重要性
オホーツク海の氷が減少すると、養分に富んだ海流が弱まり、広大な北太平洋に生息する海洋生物たちが危険にさらされる。この事実は、これまで観測された気候変動の影響としては最も驚くべきものであると同時に、最も議論されてこなかったものでもある。
河川で卵から孵化した稚魚は、春、雪解け水とともに海に降り、8月~11月までオホーツク海で過ごします。その後大西洋西部へ移動し、冬を越します。夏になるとベーリング海に回遊し、餌を捕食しながら大きく成長します。11月頃になると南下し、アラスカ湾へ移動し冬を越します。その後夏はベーリング海、冬はアラスカ湾を行き来します。そして4年後、成熟魚になった鮭は、ベーリング海から千島列島沿いに南下し、9月~12月頃、それぞれ日本の生まれ故郷の河川へと帰るのです。外洋での長旅を終えた鮭は、産卵のために故郷の河川を遡上します。遡上を終えた鮭は、雄、雌つがいとなり、川底に産卵床をつくります。その中へ雌が産卵、雄が放精し、受精卵が形成されます。そして繁殖という役目を終えた鮭は力尽きてしまいます。鮭が生まれた川に帰ってくることを『母川回帰』と言います。
広い広い外洋に出た鮭はなぜ母川回帰することができるのでしょうか?これには諸説ありますが、生まれた川のにおいを覚えているという説が有力です。鼻詰めされた鮭は生まれた川へ帰れなくなったという実験結果もあります。川のにおいとは、数十種類のアミノ酸の組成によって決まるそうです。ただし、遠く離れた外洋から故郷の川のにおいを嗅ぎわけることは不可能に近いと思われるので、他の方法も併用していると考えられています。太陽コンパスを利用する説、磁気を感知する説、海流に乗り移動する説などがありますが、はっきりしたことはわかっていません。未だにまだ多くの謎に包まれているのです。そして、今年は海水の上昇で川に戻れないさけが海に留まっていると考えられますが、川に遡上して産卵しなければ、さけは増えないのでは?サケも戻りたいけど戻れない。川から遠い冷たい海域で何をかんがえているのだろうか?
(食養指導士 三橋敏次 拝)