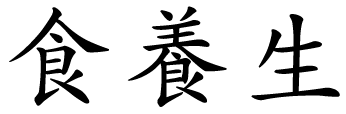和田洋巳教授

元京大医学部教授が提言 全身転移でもがんと共存できる!
2018年6月24日号
集中連載 がん患者が殺到する医院! がん制圧の法則/5
現在では4期のがん患者の25%が劇的寛解を得ている―。7年前、京都市内にクリニックを開設した元京都大教授の和田洋巳医師(75)が明かした衝撃的なデータは、がん治療の未来を示す福音となるのだろうか。連載第5回では、和田医師が模索するがん治療の根源に迫っていく。
前回の6月3日号では、和田洋巳医師(75)が女性スタッフらとともに考案した「和田屋のごはん」について、「がんが住みにくい体をつくる」ための具体的な献立例やレシピなどを交えて詳しく紹介した。
実際、「からすま和田クリニック」では、食生活の改善を中心とする独特の治療戦略によって、4期のがん患者から目を見張る数の長期生存例が続出。開設から7年が経過した今、その割合は4期患者の25%にも達している(注1)。
通常、最終病期にあたる4期のがんは「治癒不能」とされ、事実上、残された手段は抗がん剤による延命治療のみ。だが、和田医師は「そもそも、がん治療については、『治る』『治らない』の二元論で考えるべきではない」と力説する。
3週ぶりに再開する衝撃連載の第5回は、連載回数を全6回とした上で、前回で予告した内容を少し変更し、和田医師が目指す「長期生存」と標準がん治療でいう「延命」との根本的な違いも含めた「劇的寛解とは何か」にズバリ迫る。
※
―開設以来、和田先生のクリニックでは、主に食生活の改善によって、4期のがん患者の約25%、数にして約300人が、標準がん治療ではまず考えられない長期生存を果たしている、ということでしたね。
和田 しかも、年々、治療成績は向上してきており、近い将来、4期患者に占める長期生存の割合は3割に達するのではないかと見ています。当然、治療成績は原発がんの種類によって違ってきますが、例えば他臓器などへの転移がある4期の肺がんの場合(注2)、転移が見つかってから5年を超えて長期生存している患者さんの割合は6割にまで向上しつつあります。
―これまた驚異的な数字ですが、がんは正常細胞の遺伝子が変異することで発生します。その遺伝子変異をもたらす大きな要因として悪い食習慣がある点は理解できますが、いったん変異してしまった遺伝子を食生活の改善で正常に戻すことはできないのでは?
和田 その点については、「がんが治る」ということをどのように捉えるか、にかかっていると、私は考えています。標準がん治療の場合、外科手術によって転移のない原発がんを取り除き、手術からおおむね5年間、転移が出てこなければ「がんは治った」とされます(注3)。私もこの点については基本的に異論はありませんが、一方、手術後に転移が出てしまった場合は、急転直下、一足飛びに「このがんは治らない」と宣告されてしまうのです。
―しかも、後者の場合、患者は延命を名目とした抗がん剤治療に引きずり込まれて苦しみ、中には抗がん剤の毒性によって急死してしまう患者もいます。
和田 京大病院時代、転移が見つかった4期の患者さんに対しては、私も抗がん剤を使った治療を行っていました。ゆえに偉そうなことを言うつもりはありませんが、私がみずからの過去への反省も込めて最も問題だと感じているのは、標準がん治療には「治る」と「治らない」の間に存在すべき概念がスッポリと抜け落ちている点なのです。
―中間にあるべき概念?
和田 がんを「治る」「治らない」の二元論で捉えるから間違いが起こる。実は、人は体の中にがんがあるだけでは死にません。たとえ、がんが全身に転移してしまったとしても、全身にがんがあるという理由だけで死ぬわけではないのです。
◇「治る」「治らない」二元論から脱却を
―ならば、人はなぜがんで亡くなるのですか。
和田 それは、例えば他臓器に転移したがんが増殖して臓器不全を引き起こすからです。肝臓なら肝不全、腎臓なら腎不全です。あるいは、腹膜(注4)に散らばったがんが増殖し、小腸や大腸などの消化管を圧迫して、通過障害を引き起こすからです(注5)。典型は腸閉塞(へいそく)です。通過障害ならバイパス手術(注6)などで一時的な対処が可能な場合もありますが、逆にいえば、がんがこのような臓器不全や通過障害などの”悪さ”さえしなければ亡くなることはないのです。がん自体が何か人を死に至らしめる毒などを出しているわけではありませんから。
―つまり、「治る」「治らない」の二元論ではなく、がんが悪さをしない状況をつくり出せばいいと?
和田 そのような状況、すなわち「がんが住みにくい体」を食生活の改善を中心につくり出し、標準がん治療ではおよそ考えられない長期生存を実現する、というのが私の戦略です。そして、私が「劇的寛解」と呼んでいる状況がまさしくこれで、先ほど指摘した「治る」と「治らない」の間を埋めることになる全く新しい考え方なのです。
―ただ、「寛解」という概念自体は、標準がん治療にも存在していますね。
和田 主として抗がん剤治療の効果判定の際に用いられる概念です。例えば、がんが縮小すればPR(パーシャル・レスポンス=部分寛解)、がんが消失すればCR(コンプリート・レスポンス=完全寛解)などと判定されます。しかし、仮に抗がん剤治療でPRやCRが得られたとしても、多くの場合、抗がん剤耐性を獲得したがんがこれまで以上の勢いで暴れ出してしまうため、私が目指している劇的寛解のような長期生存は望めません。実際、転移が見つかって抗がん剤治療を受けた場合、大半の患者さんが1~2年以内に亡くなってしまうのです。
―なぜ「がん」は抗がん剤に対する「耐性」を獲得してしまうのでしょうか。
和田 この点については、数多くの研究論文が発表されてきました。この際、難しい理屈は省略しますが、読者にもわかりやすい最も代表的で重要な知見を一言で紹介すれば、「がん細胞周辺の微細環境が酸性に傾くと、がんは抗がん剤耐性を獲得しやすくなる」ということがわかってきています。前回、私のクリニックに来られる患者さんの話として、抗がん剤治療がどうしても避けられない場合、治療を受ける7日ほど前から食事を「和田屋のごはん」の「とっておきのごはん」に変えると、治療の効果が上がるケースがあることを紹介しました。このような効果が得られるのも、食事によってがん細胞周辺の微細環境が酸性からアルカリ性へと変化し、がんが抗がん剤耐性を獲得しにくくなったからだと考えられるのです。
◇「苦しみながらの延命は意味ない」
―ところが、標準がん治療では、ある抗がん剤が効かなくなると別の抗がん剤を使う、という治療が延々と繰り返されます。
和田 がんの治療ガイドライン(注7)にも収載されている抗がん剤の「乗り換え治療」の場合、事実上、治療は患者さんが毒性死するまで続けられるか、毒性死の直前に患者さんを緩和ケアに送り込むか、になります。そういえば、この乗り換え治療を巡る信じ難いエピソードについて、以前、森さんは私に話してくれたことがありましたね。
―はい。有名な某大学病院で乗り換え治療を受けていた患者が亡くなった時の話です。その直後、担当医は遺族に遺体の解剖を願い出て了承されました。果たせるかな、遺体を解剖してみると、がんが完全に消失していた。小躍りして喜んだ担当医はすぐに遺族を呼び、満面に笑みまでたたえながら「見てください。がんは完全に消えています。抗がん剤は効いていたんです。よかったですね!」と叫んだというのです。
和田 まさしく本末転倒の極みですね。この担当医は患者さんが亡くなったという最も重大な事実に関心がないばかりか、悲しみに暮れる遺族に抗がん剤が効いていたという事実を自慢げに話している。この担当医にとって、患者さんが抗がん剤の乗り換え治療で苦しみ抜いた揚げ句に亡くなってしまったことなど、どうでもいいわけです。抗がん剤が効いていたことさえわかればそれでいい。亡くなった患者さんやご遺族には申し訳ない表現になりますが、さすがにここまでくると悲劇を通り越して喜劇と言わざるを得ません。
―程度の差こそあれ、標準がん治療で言う「抗がん剤が効いた」とは、こういうことだったんですね。
和田 患者さんが苦しもうが亡くなろうが、とにかくがんが縮小、消失すればそれでオーケー。つまり、がんの縮小や消失が自己目的化しているのです。もちろん、私が目指す劇的寛解においても、がんが縮小、消失するならば、それに越したことはありません。しかし、たとえ縮小や消失が得られなくても、がんが暴れ出さない状態、つまり悪さをしない状態をつくり出せば、乗り換え治療などではまず考えられない長期生存が可能になるのです。
―しかも、その場合、患者のQOL(クオリティー・オブ・ライフ=生活の質)は極めて高く保持されているわけですからね。
和田 その点はとても重要です。仮に抗がん剤治療が奏功して、がんの縮小や消失が得られたとしても、亡くなるまでの間、患者さんは毒性に苦しみ続けます。個々の患者さんの死生観などによっても事情は違ってきますが、少なくとも私は苦しみながらの延命では意味がないと考えています。一方、私のクリニックで劇的寛解を得ている患者さんの大半は、原則、現に投与を受けている抗がん剤の減薬、可能なら完全な断薬を試みながら、食生活の改善を中心とする治療を続けているため、健康な人たちとほぼ変わらないQOLを維持できているのです。
―全身にがんが広がってしまったような場合でも、高いQOLを保ちながらの長期生存は可能ですか?
和田 そういう患者さんはたくさんおられます。例えば、がん性胸膜炎や全身骨転移などのあった肺がん4期の患者さん(50歳代後半の男性)。私のクリニックでの初診は2013年7月ですが、前述した微細環境をアルカリ性に変える食生活の改善などに取り組んだ結果、現在では全身のPET検査(注8)でもがんの異常集積は全く見られなくなり、元気に社会生活を送っておられます。あるいは、黄疸(おうだん)や肝転移などのあった十二指腸乳頭部がん4期の患者さん(70歳代前半の男性)。当クリニックでの初診は14年5月のことで、その後、各腫瘍マーカー(注9)の値が徐々に低下するとともに、肝臓にあった転移病巣も縮小→消失するに至って、先の患者さんと同じく、現在は仕事ができるまでに回復しています。
この続きは2018年6月24日号本誌をご購入ください。
2018年6月24日号
集中連載 がん患者が殺到する医院! がん制圧の法則/5
現在では4期のがん患者の25%が劇的寛解を得ている―。7年前、京都市内にクリニックを開設した元京都大教授の和田洋巳医師(75)が明かした衝撃的なデータは、がん治療の未来を示す福音となるのだろうか。連載第5回では、和田医師が模索するがん治療の根源に迫っていく。
前回の6月3日号では、和田洋巳医師(75)が女性スタッフらとともに考案した「和田屋のごはん」について、「がんが住みにくい体をつくる」ための具体的な献立例やレシピなどを交えて詳しく紹介した。
実際、「からすま和田クリニック」では、食生活の改善を中心とする独特の治療戦略によって、4期のがん患者から目を見張る数の長期生存例が続出。開設から7年が経過した今、その割合は4期患者の25%にも達している(注1)。
通常、最終病期にあたる4期のがんは「治癒不能」とされ、事実上、残された手段は抗がん剤による延命治療のみ。だが、和田医師は「そもそも、がん治療については、『治る』『治らない』の二元論で考えるべきではない」と力説する。
3週ぶりに再開する衝撃連載の第5回は、連載回数を全6回とした上で、前回で予告した内容を少し変更し、和田医師が目指す「長期生存」と標準がん治療でいう「延命」との根本的な違いも含めた「劇的寛解とは何か」にズバリ迫る。
※
―開設以来、和田先生のクリニックでは、主に食生活の改善によって、4期のがん患者の約25%、数にして約300人が、標準がん治療ではまず考えられない長期生存を果たしている、ということでしたね。
和田 しかも、年々、治療成績は向上してきており、近い将来、4期患者に占める長期生存の割合は3割に達するのではないかと見ています。当然、治療成績は原発がんの種類によって違ってきますが、例えば他臓器などへの転移がある4期の肺がんの場合(注2)、転移が見つかってから5年を超えて長期生存している患者さんの割合は6割にまで向上しつつあります。
―これまた驚異的な数字ですが、がんは正常細胞の遺伝子が変異することで発生します。その遺伝子変異をもたらす大きな要因として悪い食習慣がある点は理解できますが、いったん変異してしまった遺伝子を食生活の改善で正常に戻すことはできないのでは?
和田 その点については、「がんが治る」ということをどのように捉えるか、にかかっていると、私は考えています。標準がん治療の場合、外科手術によって転移のない原発がんを取り除き、手術からおおむね5年間、転移が出てこなければ「がんは治った」とされます(注3)。私もこの点については基本的に異論はありませんが、一方、手術後に転移が出てしまった場合は、急転直下、一足飛びに「このがんは治らない」と宣告されてしまうのです。
―しかも、後者の場合、患者は延命を名目とした抗がん剤治療に引きずり込まれて苦しみ、中には抗がん剤の毒性によって急死してしまう患者もいます。
和田 京大病院時代、転移が見つかった4期の患者さんに対しては、私も抗がん剤を使った治療を行っていました。ゆえに偉そうなことを言うつもりはありませんが、私がみずからの過去への反省も込めて最も問題だと感じているのは、標準がん治療には「治る」と「治らない」の間に存在すべき概念がスッポリと抜け落ちている点なのです。
―中間にあるべき概念?
和田 がんを「治る」「治らない」の二元論で捉えるから間違いが起こる。実は、人は体の中にがんがあるだけでは死にません。たとえ、がんが全身に転移してしまったとしても、全身にがんがあるという理由だけで死ぬわけではないのです。
◇「治る」「治らない」二元論から脱却を
―ならば、人はなぜがんで亡くなるのですか。
和田 それは、例えば他臓器に転移したがんが増殖して臓器不全を引き起こすからです。肝臓なら肝不全、腎臓なら腎不全です。あるいは、腹膜(注4)に散らばったがんが増殖し、小腸や大腸などの消化管を圧迫して、通過障害を引き起こすからです(注5)。典型は腸閉塞(へいそく)です。通過障害ならバイパス手術(注6)などで一時的な対処が可能な場合もありますが、逆にいえば、がんがこのような臓器不全や通過障害などの”悪さ”さえしなければ亡くなることはないのです。がん自体が何か人を死に至らしめる毒などを出しているわけではありませんから。
―つまり、「治る」「治らない」の二元論ではなく、がんが悪さをしない状況をつくり出せばいいと?
和田 そのような状況、すなわち「がんが住みにくい体」を食生活の改善を中心につくり出し、標準がん治療ではおよそ考えられない長期生存を実現する、というのが私の戦略です。そして、私が「劇的寛解」と呼んでいる状況がまさしくこれで、先ほど指摘した「治る」と「治らない」の間を埋めることになる全く新しい考え方なのです。
―ただ、「寛解」という概念自体は、標準がん治療にも存在していますね。
和田 主として抗がん剤治療の効果判定の際に用いられる概念です。例えば、がんが縮小すればPR(パーシャル・レスポンス=部分寛解)、がんが消失すればCR(コンプリート・レスポンス=完全寛解)などと判定されます。しかし、仮に抗がん剤治療でPRやCRが得られたとしても、多くの場合、抗がん剤耐性を獲得したがんがこれまで以上の勢いで暴れ出してしまうため、私が目指している劇的寛解のような長期生存は望めません。実際、転移が見つかって抗がん剤治療を受けた場合、大半の患者さんが1~2年以内に亡くなってしまうのです。
―なぜ「がん」は抗がん剤に対する「耐性」を獲得してしまうのでしょうか。
和田 この点については、数多くの研究論文が発表されてきました。この際、難しい理屈は省略しますが、読者にもわかりやすい最も代表的で重要な知見を一言で紹介すれば、「がん細胞周辺の微細環境が酸性に傾くと、がんは抗がん剤耐性を獲得しやすくなる」ということがわかってきています。前回、私のクリニックに来られる患者さんの話として、抗がん剤治療がどうしても避けられない場合、治療を受ける7日ほど前から食事を「和田屋のごはん」の「とっておきのごはん」に変えると、治療の効果が上がるケースがあることを紹介しました。このような効果が得られるのも、食事によってがん細胞周辺の微細環境が酸性からアルカリ性へと変化し、がんが抗がん剤耐性を獲得しにくくなったからだと考えられるのです。
◇「苦しみながらの延命は意味ない」
―ところが、標準がん治療では、ある抗がん剤が効かなくなると別の抗がん剤を使う、という治療が延々と繰り返されます。
和田 がんの治療ガイドライン(注7)にも収載されている抗がん剤の「乗り換え治療」の場合、事実上、治療は患者さんが毒性死するまで続けられるか、毒性死の直前に患者さんを緩和ケアに送り込むか、になります。そういえば、この乗り換え治療を巡る信じ難いエピソードについて、以前、森さんは私に話してくれたことがありましたね。
―はい。有名な某大学病院で乗り換え治療を受けていた患者が亡くなった時の話です。その直後、担当医は遺族に遺体の解剖を願い出て了承されました。果たせるかな、遺体を解剖してみると、がんが完全に消失していた。小躍りして喜んだ担当医はすぐに遺族を呼び、満面に笑みまでたたえながら「見てください。がんは完全に消えています。抗がん剤は効いていたんです。よかったですね!」と叫んだというのです。
和田 まさしく本末転倒の極みですね。この担当医は患者さんが亡くなったという最も重大な事実に関心がないばかりか、悲しみに暮れる遺族に抗がん剤が効いていたという事実を自慢げに話している。この担当医にとって、患者さんが抗がん剤の乗り換え治療で苦しみ抜いた揚げ句に亡くなってしまったことなど、どうでもいいわけです。抗がん剤が効いていたことさえわかればそれでいい。亡くなった患者さんやご遺族には申し訳ない表現になりますが、さすがにここまでくると悲劇を通り越して喜劇と言わざるを得ません。
―程度の差こそあれ、標準がん治療で言う「抗がん剤が効いた」とは、こういうことだったんですね。
和田 患者さんが苦しもうが亡くなろうが、とにかくがんが縮小、消失すればそれでオーケー。つまり、がんの縮小や消失が自己目的化しているのです。もちろん、私が目指す劇的寛解においても、がんが縮小、消失するならば、それに越したことはありません。しかし、たとえ縮小や消失が得られなくても、がんが暴れ出さない状態、つまり悪さをしない状態をつくり出せば、乗り換え治療などではまず考えられない長期生存が可能になるのです。
―しかも、その場合、患者のQOL(クオリティー・オブ・ライフ=生活の質)は極めて高く保持されているわけですからね。
和田 その点はとても重要です。仮に抗がん剤治療が奏功して、がんの縮小や消失が得られたとしても、亡くなるまでの間、患者さんは毒性に苦しみ続けます。個々の患者さんの死生観などによっても事情は違ってきますが、少なくとも私は苦しみながらの延命では意味がないと考えています。一方、私のクリニックで劇的寛解を得ている患者さんの大半は、原則、現に投与を受けている抗がん剤の減薬、可能なら完全な断薬を試みながら、食生活の改善を中心とする治療を続けているため、健康な人たちとほぼ変わらないQOLを維持できているのです。
―全身にがんが広がってしまったような場合でも、高いQOLを保ちながらの長期生存は可能ですか?
和田 そういう患者さんはたくさんおられます。例えば、がん性胸膜炎や全身骨転移などのあった肺がん4期の患者さん(50歳代後半の男性)。私のクリニックでの初診は2013年7月ですが、前述した微細環境をアルカリ性に変える食生活の改善などに取り組んだ結果、現在では全身のPET検査(注8)でもがんの異常集積は全く見られなくなり、元気に社会生活を送っておられます。あるいは、黄疸(おうだん)や肝転移などのあった十二指腸乳頭部がん4期の患者さん(70歳代前半の男性)。当クリニックでの初診は14年5月のことで、その後、各腫瘍マーカー(注9)の値が徐々に低下するとともに、肝臓にあった転移病巣も縮小→消失するに至って、先の患者さんと同じく、現在は仕事ができるまでに回復しています。
この続きは2018年6月24日号本誌をご購入ください。